
あなたの会社に社歌はありますか?
ああそういえばあったかも、という会社や、ウチにはそんなものないよ、という会社、ウチは毎日朝礼の時に歌っているよ、という会社など、様々でしょう。
そもそも社歌と聞くと、「歌いたくない」とか「押し付けがましい」とか「あるけど歌う機会がない」などというご意見も決して少なくないと思います。
もちろん、自分の会社の社歌に愛着を持ち、「大好きだ」という方もいらっしゃることでしょう。でも、あまり好きじゃない、という方が決して少なくないのはなぜでしょう?どうして社歌は皆から好かれないのでしょうか?
社歌が好きではないという人の意見を聞いてみると、次の2つの理由が存在します。
●「古臭い」「ダサい」というように楽曲そのものに対する否定的な意見
●「斉唱を強制される」といった運用の姿勢や方法に対する嫌悪の意見
前者の意見の方は、音楽自体は好きだけどダサいものはイヤ、というように嗜好の問題であり、したがって、楽曲そのものが見直されれば、もしかすると好感度が上がるという可能性は残されています。
一方の後者の意見の多くは、そもそも「歌を歌うことが嫌い」であることが多いので、たとえ楽曲を見直したところで、斉唱を強制する運用ルールがある限り、好かれる可能性は高まらないとも言えるでしょう。
ただし、社歌というのは組織の一員の帰属感や絆、一体感などを醸成する上では、実は非常に効果的なコミュニケーションツールであるとも言えるのです。もともと社歌は、製造業の現場で工員たちの士気を高め、娯楽の一つにもなりうる目的で作られたものですが、これまでの社歌の歴史的背景からいえば、景気が極端にいいか極端に悪い時期に社歌がブームが起きていることがわかります。
日本での最初に社歌ブームは、戦前の世界恐慌の時代で、社員一丸となって不況を乗り越える目的で多くの企業が社歌を作りました。次は戦後の高度成長期で、労働者の団結を促し右肩上がりの企業の成長を後押しする原動力となる目的で多くの歌が作られました。そして3回目のブームがバブル期であり、CI(コーポレートアイデンティティ)ブームブランディングの一環として多くの企業が著名なアーティストなどに依頼して社歌を作ったのでした。
そして昨今、実は4回目の社歌ブームの時代であるとも言われています。これは東日本大震災以降、全国的にあらためて「絆」の意義を問う動きが盛んになるとともに、動画投稿サイトやSNSの普及に伴い、企業のPR活動のツールや環境が自由な広がりを見せ始めたことに起因します。
多くの企業で、社員が率先して歌作りに参加して様々なジャンルの楽曲を作り、さらにはそこに振り付けを施して社員全員はもちろん役員や社長までも参加して一緒に踊ってそれを動画投稿サイトにアップしたりなど、従来の社歌の枠に収まらない自由な活動が盛んに行われました。それが結果的に企業のブランドイメージを上げ、リクルーティング効果を生み、業績向上にも繋がるなど、想定以上のプラス効果を生み出しているのです。
現代の社歌ブームを支えている理由には、
●社員が歌作りに参加している
●「社歌」というより、「応援歌」「テーマソング」「イメージソング」などのスタンスで作られている
●従来の社歌の概念やスタイルに縛られず、ジャズ、ロック、ポップス、テクノ、ヒップホップ、レゲエなど自由な作風やジャンルで作られている
●振り付けやダンスを伴い社員で踊ったりすることで、「映像作品」として残される
●「歌ってみた」「踊ってみた」などのタイトルで、自社のWebサイトやSNSを通じて広く拡散、シェアされる
などといった特徴が挙げられます。
もちろん、社員に斉唱を強制するようなこともほとんどありません。そこに共通するのは、歌うことを強制するよりも、皆が自主的に歌いたくなる、踊りたくなる、参加したくなる、そのような空気を作り出すことが重要だという認識。
そして企業が新しく社歌(あるいは応援歌、テーマソング、イメージソング)を作る絶好のタイミングとして、「周年」という機会が最適であるとも言われています。
いかがでしょうか?私たち「周年太郎」では、周年事業のメニューのひとつとして「社歌の制作」というサービスを提供しています。御社の周年事業の施策の一つとして、ぜひトライしてみてください!

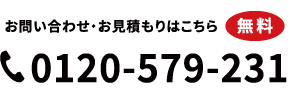





[…] […]